「憲法」も「律令」も「詔勅」もノリ
古代においては「憲法」「律令」「格式」「詔書」「勅書」はいずれも、大和言葉で「ノリ」と訓みます。聖徳太子の作と伝えられる、7世紀初めの「憲法」十七条は、天皇に仕える臣僚(官人)が守るべき規範でありました。また、8世紀初めの大宝・養老年間にできました「律令」も、9世紀初めから三代にわたり編纂された「格式」にしても、中央・地方の官人の庶民たちが守らなければならない規則でした。
さらにいえば、そうした古代の「憲法」や「律令」「格式」の上に立つ「天皇」(和訓はスメラミコト)から臣民らに対して口頭で「宣告」(ノリ)される「お言葉」は、最高の「ノリ」であり、それを文書で示される「詔書」や「勅書」も、「宣命」「宣旨」も、みな「ミコトノリ」にほかなりません。
これが何よりも重要なことは、聖徳太子「十七条憲法」(原漢文)の第三条に、次のように示されております。
「詔を承けては必ず謹め(承詔必謹)。君は則ち天なり、臣は則ち地なり。天覆ひ地戴す。……君言たまへば民承はり、上行へば下靡く。故に、詔を承けては必ず慎め。謹まざれば自ら敗れん。」
この「承詔必謹」という考えは、古代以来、1400年以上にわたり、わが国の為政者たち(貴族も武家も)が原則として守るべき掟とされ、また一般庶民の多くも、それを日本人の心得としてきました。

日本的な「神祇令」と「継嗣令」の特色
ほぼ7世紀代に準備を進め、8世紀初めに公布された日本の「律令法」は、制定・修正当時の年号を冠して「大宝律令」(701年)・「養老律令」(718年)と称されます。それは、おもに唐代の律令を手本にして作成されたものですから、おおまかな原則は双方共通していますが、日本的な特色も盛り込まれています。
例えば、律(刑法)も令(行政法)も、皇帝・天皇が主体となって制定する規則なので、皇帝・天皇はそれに拘束されません。現に唐と日本の「名例律」では、「非常の断、人主これを専らにす」と注記しています。それゆえ、太政官・刑部省が大罪人の「死刑」を決定しても、上奏を御覧になる天皇が執行を許可されないかぎり死刑は執り行われず、平安時代には300年近く公的な死刑は執り行われませんでした。
一方、日本令は、唐令と違って、一般行政を司る「太政官」とは別に、神祇行政を司る「神祇官」を設けています。そして、「神祇令」を「僧尼令」より前に置き、たとえば天皇の即位に際してのこととして次のように定めております(原漢文)。
「およそ天皇即位したまふときは、惣て天神地祇を祭れ……。」(天神地祇条)
「およそ踐祚の日、中臣が天神の寿詞を奏し、忌部が神璽の鏡剣を上れ。」(践祚条)
「およそ大嘗は、世(一代)毎に一年、国司(悠紀・主基の両国)が事を行へ。以外(新嘗祭)は年(一年)毎に所司(神祇官)が事を行へ。」(大嘗条)
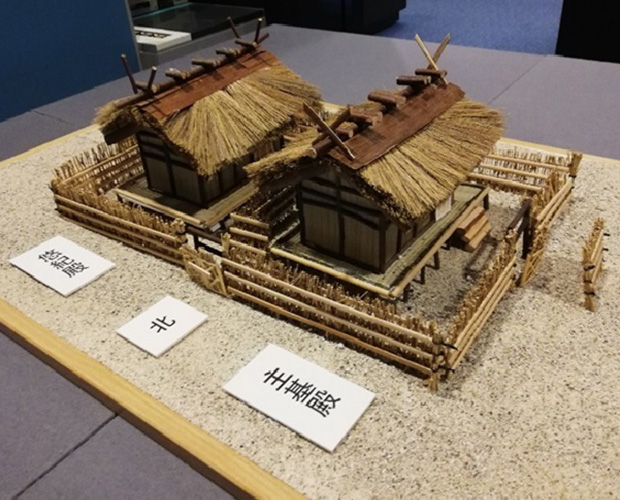
また、日本の「継嗣令」は、唐の「封爵令」を手本にしています。しかしながら、唐令では、皇帝が諸侯に官爵を授ける規定を中心にしたものであるのに対して、日本令では、皇族身分の範囲や貴族(三位以上)と准貴(四・五位)の継承と婚姻に関する規定であり、著しい違いが見られます。
(本稿は所功『象徴天皇「高齢譲位」の真相』ベスト新書の一部を抜粋・加筆したものです)
